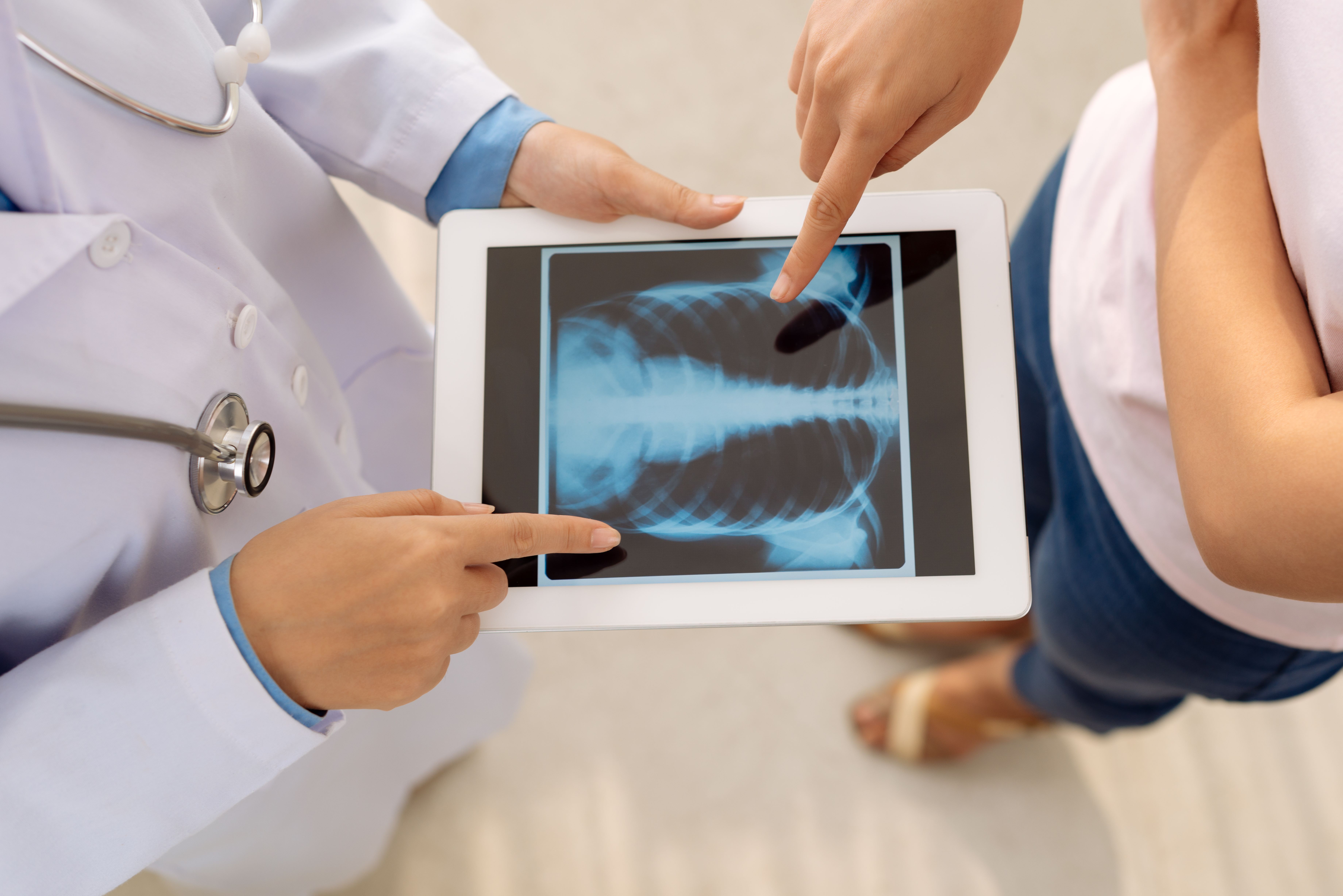連載:CES2023を読み解く~テクノロジーの未来はそこにあるか?~
Vol.4DX先進メーカーの「変革の起点」と日本企業への示唆
- 2023年5月
連載:CES2023を読み解く~テクノロジーの未来はそこにあるか?~
Vol.4DX先進メーカーの「変革の起点」と日本企業への示唆
- 2023年5月
先進メーカーに見る DX推進の4タイプ
現在、正式名称にもなった”CES”であるが、初開催から長らくは”Consumer Electronics Show”が会の名称であった。日本ではこの訳として「家電見本市」が今も一般的である。そのため、今でも「家電メーカーが一堂に会するイベント」というイメージを持っている人もいるかもしれない。だが実際は、メーカーに限らず様々な企業が参加している。メーカーも消費者向け(B2C)だけではない。今回はビジネス向け(B2B)を主力とするメーカーを取り上げる。
所狭しと数多のメーカーがひしめき合う中、ひと際目を奪われたのは、最前線でDXに取り組み、来場者の期待を超えるようなコンセプトや製品を打ち出す企業や、新領域に挑戦する企業であった。彼らは、自社独自の工夫でDXを推進することで、自社の可能性を最大限発揮し、常に進化を続けている。
多くの企業、特に日本企業では「競合がやっているから」や「世間の潮流に乗り遅れないように」といった、ある種の”危機感”がDX推進の動機付けになっていることが少なくない。しかし、それだけでは常に後手に回ってしまうだろう。では、今回のCESで異彩を放っていた企業はいかにして最前線でDXを推進できているのだろうか。
先進メーカーの展示やヒアリングから、彼らはDXを推進するツボである『変革の起点』を上手く生かしていることが分かった。この起点は企業によって様々であるが、主に4つのタイプが見られた。本稿では、この4つのタイプ別の企業事例を通じながら、先進企業における起点を活かしたDX推進を読み解いてこう。その要諦は製造業のみならずDXに挑むあらゆる日本企業への学びとなるはずだ。
それぞれ簡単に説明しておくが、次節で具体的に解説するので、ここではイメージをつかむだけで構わない。

- 戦略ドリブンDX:
事業戦略を起点に、新規事業の開発や新規市場への参入を狙うDX - 企業文化ドリブンDX:
新しい事への自発的な挑戦を促進する企業文化を起点とするDX - ディスラプションドリブンDX:
既存の事業・業界のディスラプションを起点とするDX - 顧客ニーズドリブンDX:
顧客のニーズを起点に、それに応える手段として活用されるDX
タイプ別 先進企業事例
1.戦略ドリブンDX: Siemens
産業のデジタル化が推進される中、SiemensはMindSphereに代表される従来の「製造業向けのテクノロジー企業」というブランドイメージから脱却し、あらゆるユーザーへのソリューション提供に舵を切った。この実現に向け、事業戦略の中核に据えられているのが2022年6月に発表されたXceleratorである。同社出展ブースの中心に展示されていたことからもその期待の高さがうかがえた。
Xceleratorは、同社が持つ100以上のソフトウェアを一元管理するオープンなプラットフォームである。各ソフトウェアはモジュール単位に分解・標準化されており、ユーザーは自身に必要なモジュールを組み合わせ、ソフトウェアを再構築することができる。これにより低価格でのカスタマイズが実現でき、業界や規模を問わずあらゆるユーザーのニーズに応えることを可能にしている。実際、従来はターゲット外であった宇宙産業や農業という、製造業以外の業界でも顧客を獲得し始めている。また、顧客の規模も大企業だけでなく中小企業や個人まで広がってきている。DXによって事業戦略を遂行し、新規事業で新規市場を獲得する好例だ。
さらに、展示ブースでは同社にとって新領域への挑戦である海中農業への取り組みが紹介されていた。栽培設備には自社デバイスを、生育管理には自社シミュレーションソフトが駆使するなど、自社の強みや技術を余すことなく活かす姿から、その覚悟が伝わってきた。あらゆる業界へデジタルソリューションを提供する戦略を文字通り体現していた展示は多くの来場者の期待を超えるものだったであろう。
2.企業文化ドリブンDX: 3M
自社内で明文化された起点である“戦略”を活かしたSiemensと対比的なのが3Mである。同社には「3Mカルチャー」という独特な不文律、すなわち企業風土・文化が存在する。
DXの好事例として挙げられることも多い同社は、間違いなくDX先進企業である。しかし、聞くところによると、経営によるDX方針の策定やDX推進組織の設置、各部署へのデジタル人材の配置が行われたのは、2021年ごろとのこと。つい最近のことだ。トップの牽引はDX推進の定石のように思えるが、それ無くしてどのように同社のDXは推進されたのか。その起点こそが「3M Culture」なのである。
3Mカルチャーは不文律であるが、有名なものは名前が付けられている。その中でも同社製品の代表作Post-it(ポスト・イット)を生み出したことで、特に広く知られているのが「15% Culture」だ。将来のビジネスに役立つと考えるのであれば、業務時間の15%を自分の好きな研究に充ててよいとするものである。Googleもこれを真似てGmailを生み出したと言われるほど、最も成功した社内イノベーション策の一つである。これまでに、15% カルチャーによって社員が自発的にデジタルを活用し、商用化まで至ったプロダクトも複数生まれている。トップダウンせずとも現場から自律的に変革する風土が同社には備わっているのだ。
これだけではない。他にも、上申なしに社内チームを組成し、製品開発を進められる「Bootlegging」。これでPoC(実証)はいつでもクイックに実行できる。アイデアが会社公認となれば、立案者に対し社内使用や各種権限が与えられ、自ら裁量を持って事業化に挑める「BDU(Business Development Unit)」。これによって、既存事業と切り離した別枠での開発や事業立上げがクイックにできる。予算面も心配しなくてよい。重要なイノベーションと認定されたプロジェクトに予算を集中投下する「Basing Plus」は予算プールとして柔軟に機能している。承認を得られなかったアイデアに敗者復活として別枠予算を充てることができる「Genesis Program」という文化さえ存在する。他にもまだまだユニークな文化が存在するが、これだけ説明すれば社員による自発的なDXが生まれる文化が同社に根付いていることが分かるだろう。
展示ブースでは、最先端技術を活用したVRなど、深く感心する来場者の姿も多かった。そこで社員から聞いた意外な言葉に思わずハッとした。「我々はTech企業ではない」
彼らにとってデジタルもイノベーションを生む部品の一つに過ぎないのであろう。変革に必要な機能や仕組みはすでに、同社のイノベーション文化の中に備わっているのだろう。
3.ディスラプションドリブンDX: John Deere
ここまで紹介した戦略や文化は社内に存在する変革の起点であったが、社外にも起点を見出だすことができる。農業機械メーカーのJohn Deereは良い例だ。同社は市場動向とディスラプターの把握に努めている。この徹底したトレンドウォッチによる市場や技術の素早い目利き対応が功を奏している。
同社では、世間の潮流や市場の動向の継続的なモニタリングを通じて、同社の既存ビジネスを破壊する恐れのあるディスラプターを見極めている。デジタル・非デジタルに関わらず、脅威となりうる有望なベンチャーを買収することで、自社のケイパビリティを即時補完し、機敏に変革を進めているとのことだ。
だが、彼らの優れた点は鋭い目利きや素早い買収だけではない。同社の強みは買収後のベンチャーの持ち味を引き出す関係づくりである。同社は買収ベンチャーを取り込むという発想は持たない。買収先の優れた文化を尊重し、その技術や人材を最大限生かせるように迎え入れる。この関係作りによって、既存製品に先端技術を素早く実装できていることが高く評価されている。200年弱の歴史を持つ老舗メーカー(1837年創業)がベンチャーと同じ目線に立ち、有効な関係を築く姿には多くの企業が学ぶべきことがあるのではないだろうか。John Deereの社員いわく、優れた技術を持つベンチャー達と共にするモノづくりこそが同社のDXの中核であるという。
展示ブースの中央には、2017年に買収した農業ロボットベンチャーBlue River Technologiesが誇る最新鋭の技術を活用した自動運転除草ロボットが据えられていた。説明を求めると、Blue River Technologiesの元社員がそのブランドを背負いながら熱心に技術を解説してくれた。互いを尊重した共創関係を築いている様子が十分にうかがえる場面であった。
脅威となりえるディスラプターも共創パートナーとして迎えることで、DXを大きく加速する機会へと変えることができる。伝統的企業の謙虚だが野心的な変革は多くの企業の励みとなり、その展示に多くの来場者にとって期待以上のものに映ったであろう。
4.顧客ニーズドリブンDX: Caterpillar
最後に紹介するのは重機メーカーのCaterpillarも社外に起点を据える。だが、彼らが注目するのは競合のシーズではなく顧客のニーズだ。が 自動採掘のグローバルリーダーである同社は、鉱山機械に多大な研究開発投資を行いながら、鉱山会社等が抱える様々な課題と向き合ってきた。
鉄鉱石採掘作業には危険が伴うため、ひとたび事故や自然災害が発生すれば作業中止となり、常に多大な機会損失のリスクを抱える。さらに、近年では技術継承等の問題も相まって人材不足が深刻化し、業界の持続可能性が問われている。これらの業界・顧客課題に対し、その時々の先進技術や革新的なアイデアを試行錯誤しながらソリューション開発に挑んできたのがCaterpillarである。
1970年代の無線制御技術の活用を皮切りに様々な技術の検証・実装に試み、2010年代には採掘業務の一部自動化を実現。その後、リスク低減や省リソース化などあらゆる顧客ニーズに応えるため、必然デジタル技術を取り込んでいった。強みの自動化技術を他の機械に横展開する一方、遠隔操作や電力供給効率化を実現する新たな技術の適用も進めていった。既存DXの拡大と新規DXの開発の両輪で顧客に伴走してきたのだ。
顧客のニーズに徹底的に向き合うCaterpillarには2つの顔がある。ひとつは、目の前の顧客の課題解決に焦点を当て、あらゆるアプローチを検討できるイノベーターとしての顔である。そのために、従来の考えに固執せず、時々の新たな技術等を柔軟に取り入れる。もうひとつは、ファクトデータに基づくビジネスの選択と集中を徹底し、中長期的な投資判断をするインベスターとしての顔である。「収益性の高い成長」を謳うこの一面は、一見すると顧客の課題解決と馴染まないようにも思える。だが、その考えは至ってシンプルで、高い収益が将来の事業投資を増やし、より良い価値を顧客に提供できるというものだ。
顧客課題・ニーズに焦点を絞りつつ、新たな技術などを取り込むために広い視野を持つ。顧客の利益を最優先にしつつ、それを持続的な支援とするには自社の利益も確保する。ともすると一方に偏りがちなスタンスを両立できるバランス感覚こそが彼らの強みだ。
会場の展示には、顧客に寄り添い徹底的に課題解決を果たした実績や成果のストーリーが伴っており、来場者を十分に満足させるものだった。

日本企業への示唆 変革の起点をどこに据えるか
さて、ここまでCES 2023で目を引いた先進メーカーから見えたDXの4タイプについて企業例を通して解説した。
自社に適したDX推進のタイプは、その企業が置かれている状況や、培ってきた文化、持っている強みなどによって異なり、ここで取り上げた4タイプに当てはまらないこともあるだろう。絶対的な正解はないが、まずは自社が何をきっかけにしてDXに取り組み始めたのか、そしてDXを通してどんな変革を成し遂げたいのか、改めて問い直してみることから始めたい。
日本では、モノづくりの伝統を活かした②企業文化ドリブンDXや、おもてなしに端を発する④顧客ニーズドリブンDXといったものが語られがちであるように思える。しかし、これらの“察する”必要がある暗示的な文化やニーズを起点としたDXの推進は、一見日本らしいものであるように思える。だが、明示的でないがゆえに、扱いを誤ると過度な自前主義や過剰なスペック要求が横行し、建設的な変革を阻害しうる諸刃の剣であることを戒めておきたい。
あらためて、DXとは「変革」である。当然ながら、事業や組織、人材など企業のあらゆるものに変化が求められる。しかし、その変化の波風の中で羅針盤や道標となるのがSiemensの新たな事業戦略であり、John Deere のトレンドウォッチである。このぶれない起点が変革にレバレッジを効かせ、自社にしか実現できないDXへと導くのだろう。自社のDXの拠り所となる『起点』は強靭なものにしておきたい。
危機感による後向きの動機付けではなく、変革の起点を活かしDXの最前線を走る日本企業が増えることを願ってやまない。